聖 書
旧約聖書 イザヤ書11章6~10節(旧約1078頁)
使徒書 ヘブライ人への手紙2章1~4節(新約402頁)
説 教 「押し流されないように」 柳谷知之牧師
◆ヘブライ書の背景
6月の最後の日曜日から、ヘブライ人への手紙(ヘブライ書)をご一緒に読み進めてします。
ヘブライ書は、教会に連なる信徒が意気消沈し、キリストがこの世に勝利されたことを疑うような状況で語られた説教です。
礼拝に集う人々は減少し、迫害が激しくなり、本当にキリストを信じることは意味があることなのか、キリストは結局弱々しく十字架で磔にされて殺されただけなのではないか、といった疑いも生じていたのです。
このような感覚や思いは、この現代にもあるように感じます。
主イエスの十字架に向かう場面、十字架上での出来事を客観的に見るならば、すくなくともそれは成功ではないと考えられます。20年前ぐらいになるでしょうか。アメリカ映画で「パッション」という映画があり、日本でも上映されました。十字架刑がリアルに描かれていて、中には「もう二度と見たくない」という感想を持つ人もいました。また、クリスチャンでも、復活して天に昇るまで描いてほしかった、という感想もありました。
人は想像以上の苦難を見たり聞いたりすることに耐えきれないものかもしれません。
また、ヘブライ人への手紙が、迫害の中にあった人々に語られたのだとすると、迫害について考えさせられます。ローマ時代の迫害によって殺されるキリスト者は、十字架刑やライオンと戦わせられその餌食になりました。無残にも殺されていく仲間たちを目の当たりにした生き残った者達は、神の全能さに疑いを持つ者たちも少なからずいたはずです。また、遠藤周作の『沈黙』という作品を想い起こします。「潜伏キリシタン」時代の拷問が描かれています。その中に「穴吊りの刑」というのがあります。いわゆるキリシタンを棄教させるために用いられた拷問です。なるべく死なないように、苦痛を長引かせる様に考え出されました。火あぶりや磔よりも残酷だと言われます。そして宣教師たちにもその刑が科せられることはありましたが、それだけでなく、「穴吊りの刑」にかかった人々のうめき声を宣教師に聞かせて、棄教させようとしました。キリシタンであっても、神は何をされているのか、と問わざるをえなかったことでしょう。
そのような中で、キリストの苦しみは弱さの象徴であり、なんの意味もなかったのではないか、と思わざるを得なくなるのです。また、迫害者から「お前たちの神は何の力もない。十字架につけられて殺された無力な存在だ」というささやきもあったのではないか、と思えます。
◆励ましの言葉
ですから、ヘブライ書の著者は、礼拝で説教をし、励ましの言葉、戒めの言葉を語ります。
「だから、わたしたちは聞いたことにいっそう注意をはらわなければなりません。」と。
「だから」という接続詞は、その前の文章から続きます。1章の終わりでは、御子キリストが、天使に優る存在であることが語られています。御子は決して無力ではない、永遠に変わることのない天地の造り主である神の右に座しておられる方である、と。そのように今もこの世界を統べ治める方として、キリストがいてくださることが説かれています。「だからこそ」主を信じる者たちは、これまで聞いてきたこと、語られてきたことにいっそう注意をする必要があるのです。
「これまで聞いてきたこと」とはいったいどのようなことでしょうか。
例えば、ローマの信徒への手紙を開きます。
パウロは、困難の中で主イエスの福音の宣教に務めて来ました。その彼が語ります。
「現在の苦しみは、将来わたしたちに現されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。」(ローマ8:18)(被造物も、わたしたちも)「体の贖われることを、心の中でうめきながら待ち望んでいます」(ローマ8:23)。「誰がわたしたちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ、復活させられた方であるキリスト・イエスが、神の右に座っていて、わたしたちのために執り成してくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことが出来ましょう。艱難か。苦しみか。迫害か。飢えか。裸か。危険か。剣か。」(ローマ8:34,35)、「主キリスト・イエスによって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできないのです」(ローマ8:39)「わたしたちすべてのために、その御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものをわたしたちに賜らないはずがありましょうか」(ローマ8:32)。
御子の苦しみは、わたしたちへの神の愛の現れであり、御子が神の右に座しておられて執り成されること、神の栄光を受けられていること、その栄光はやがてわたしたちも受けるものであることが語られています。絶望的な世界にあって、このことだけが希望なのです。
その希望のうちに留まるよう注意を促すのです。
さらにこの説教者は、律法を語ります。「天使たちを通して語られた言葉」とは「律法」を現します(使徒言行録7:38,53、ガラテヤ3:19)。律法の効力によって、不従順な者達が罰を受けた、ということは、ここでは出エジプトの時に、恐れのために約束の土地に入る事をためらったことが示されているようです。イスラエルの民がそのために40年間荒れ野をさまよいました。もっともこれは単なる罰ではなく、神による荒れ野での訓練と捉えることができますので、律法がゆるぎないものとなるところで、神は信仰者を鍛えられる、と言えるでしょう。そして、ヘブライ書を聞く人々にとっても、神の「大きな救い」をおろそかにするならば、さらに試練は増し加えられるのです。
◆救いの希望に向かって
説教者は、救いが確かでゆるぎないものであることを、聴き手に対して強調します。
救いは、主が最初に語られ、それを聞いた人々によって確かなものとされているのです(3節)。その救いについて、神は、聖霊の働きによって、さまざまなしるしや不思議な業、奇跡によって証されているのです。
わたしたちも苦難を抱えています。うわべでは、平穏で苦労なく暮らしているように見えたとしても、日々きつい戦いを経験していることでしょう。人間関係の破綻、病や障害、体力や気力の衰え、政治や経済の行き詰まり、自分の居場所がどこにもないと思えるような状況…。「その一生の間、食べることさえ闇の中、悩み、患い、怒りは尽きない」(コヘレト5:16)としかいいようのない日々があります。
しかし、一方、私たちも奇跡を経験しています。自然の法則と異なるような奇跡はめったにありませんが、私たち自身が主イエスに出会い、神に捉えられたこと。これは大いなる奇跡ではないでしょうか。
人間の力のむなしさに絶望しつつも、神によりどころを与えられていること。これは大変不思議なことです。決して私たちが清く、正しく、美しいからではありません。むしろ、弱さを抱え、恥じ入るしかない経験もしていることでしょう。
だからこそ、主イエスの十字架の出来事は、心に響くものとなってきているはずです。神の完全さを現された方が、無残にも十字架で殺されてよいわけはありません。「こんなことがあってよいのだろうか」と誰もが思うことでしょう。そして、その心の叫びは、決して無駄に終わることはありませんでした。個人的なところに留まるようなものではなかったことが示されています。
それが教会の存在です。
主イエスの弟子たちが、復活の主と出会い、天に昇られるところを見た後、聖霊に満たされたこと。その出来事が教会を生み出してきました。迫害の歴史を超え、また自らの罪深い歴史にも耐えつつ、教会が歴史の中で残ってきました。教会は世界の平和のために用いられたいと願っています。神の国の希望を担う場となろうとしています。聖書が語りかけることが、わたしたちを神に立ち帰らせるからです。そのようにして、聖霊に導かれ、主イエスが共に働いてくださるのです。
私たちの苦難をよくご存じの主が共にいてくださる。それゆえに、わたしたちも苦難を絶望的にとらえる必要はありません。真実を知るがゆえに経験する苦難があり、闇の現実があるからこそ、主の光による導きが確かにされていくのです。
私たち一人一人が、世にあって、希望をもって主を証する道に導かれているのです。


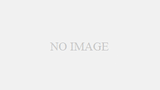

コメント